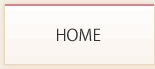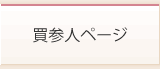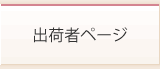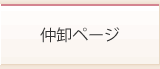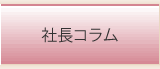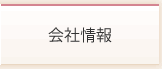IndexNo:184:今までのやり方が通用しない時代。
|
先日、ある地区の生産者の忘年会に呼ばれた時の事を今回は報告したいと思う。Aさんは、バブルの時代を経験した県内でもトップレベルの生産農家である。Aさんは、あの時の状況をこう語ってきた。「何でも作れば売れるし、収入も多く、どんどん面積を増やせることができた。パートさんも増やして、毎年のように収入が増えたときだった」と。今では、単価は3分の1、生産施設は量は作れず遊ばせている、パートもリストラしても、非常に経営が厳しい。そして、最後に涙ながらに「あの良かった時代に、こうなることを創造できなかった。すべての投資を考えるべきだった。良いときの支払計画が、今になってみれば地獄だ」と言われた。 たしかに、誰が予想できたものか。支払計画の失敗をした人を、数多く見てきている。エリートを揃えた大企業でも失敗した時代なのだ。しかしながら、そのAさんは自分の過去の失敗を理解して反省されていた事実は間違いないことであるし、現在は、反省を元に、少しずつでも収入が増えてきているという。 会社経営者として、最悪の事態を想定して準備することは、被害を最小限にとどめるためにも必要なことである。その対策を考えることができるのはトップの私しかいない。危機の種類や範囲は非常に幅広く、社長としてはすべての業務に対して、最悪のケースに備えなければならない。とくに中堅、中小企業では、資金力、人材の質と量、設備の規模などに余裕はほとんどないことが多い。それだけに、ちょっとしたことが引き金になり、会社的に多大なる影響を及ぼすことにもなりかねない。 何かひとつのことに頼り切っていればいるほど、それにトラブルが生じたときの被害は大きい。それに頼れなくなったらどうするのか、を想定しておくべきだ。しかし現実には、影響が大きい危機ほど、それに対する準備は不充分であることが多いのだ。「起こるかどうかわからない」あるいは「めったに起こらないであろう」と思われていることほど、それに備えることに意味があるのかどうか疑問に思われているからだ。゛とりこし苦労゛゛思い過ごし゛のために、貴重な時間を割くのはバカバカしいと、ほとんど手つかずの状態である。 しかし、根拠のない『楽観』は社長自信で危機の可能性すら見抜けない能力不足、その対策を考えられない能力不足を証明してようなものだ。もちろん重大事の発生だけが危機ではないのだが・・・・・・。 日常的に思い通りにいかないこと、つまり計画と現実との差が発生することも社長として手を打っておかなければならない危機管理のテーマである。 人間である以上、すべてを的確に予測することはできない。だからこそ、『万が一』に備え、万全の手を打っておくことが必要になってくるのである。それをしなければ、会社は滅びてしまう。私は精一杯の努力をし、会社そして業界のために結果を残していかなければならないのだ。 |