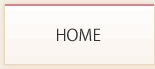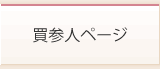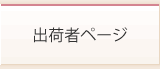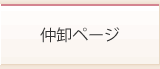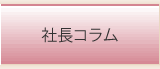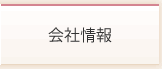IndexNo:196:花き消費を本気で考えて欲しいものだ。
|
5年前、この時期に花商さんは徹夜で卒業式の花束やアレンジづくりに追われていた。しかし、今では「学校が生徒たちの差別につながる」と花束関係のプレゼント中止になっている。先日、週刊誌にバレンタインデーのチョコレートの記事が掲載されていたが、チョコレートでも同じことが言えるのではないかと思う。「もらう生徒」「もらわない生徒」と・・・・。3年前に教育委員会に掛け合ってみたが返事は来なかった。私達花き業界には生徒のアレンジ教室を無料で頼んでくる。しかし、ひとつの協議の場では逃げ腰である。 ある「先生」と呼ばれる方で身内の方の葬儀があった。新聞紙上では「供花」お断りと書いてあった。先日、その「先生」が会社にいらっしゃたので直接、私の意見をぶつけてみたのである。「農業や商業の繁栄のために努力を惜しまない」などと言ってらっしゃるが、葬儀の供花1本でも最低5人以上の生産者の作られた花々の消費やひとつの花商さんの販売拡大につながっているのだ。その「先生」はまったく、そんなことなどに気が付いてなかったとの返事であったが・・・・・・。私たちが選んでいる「先生」だが残念である。逆に「供花を増やすから業界で頑張ってくれ」とひと言があれば、非常にリッパな「先生」であると思う。 私は、自動車の新車発表会の広告が出れば、すぐに販売会社に足を運ぶ。新車発表会のスタンド花やユーザーへの鉢物のプレゼントと商談を繰り返してきた。そのお陰で、あるT社は鉢物でも250鉢(年間7回)注文してくれるようになった。我社の車のメーカーも確実に注文をくれる。それらの注文を買参人の方々に発注するのだ。(メーカーの従来のひいき店はあるので気をつけなければいけないが)それだけで、消費拡大になっていく。ビルの建設が始まれば建設会社に連絡してみるとか。飲み会があれば、隣に座った人に「花]のことを話す。一つ一つにしてみれば、これだけのことではあるが、年間ではすごい受注量になる。前例での「先生」達が協力してくれれば、もっと花の消費は伸びるはずだ。しかし、既存の花商さんのビジネス活動がいちばん大事であることを忘れてはならない。 |