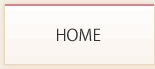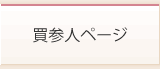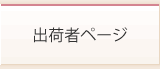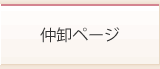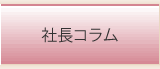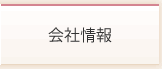IndexNo:206:国際的視野が欠けていれば発想も小さなものになる。
|
先日、ある青果卸売会社の方とお話する機会があったので今週は青果の流通と花きの流通の動向についてお話したいと思う。青果業界はここ3年間で生産、流通が大きく変化してきた。とくに輸入野菜の増大には国内の生産者、青果市場も苦戦の連続であったという。しかし、例の輸入野菜の農薬問題で量が減少して、一時は国内商品の生産、流通が元気を取り戻してきたらしいが、ここに来て輸入品のウエイトが増加してきてる状況が続いて、厳しくなるのではないかと聞かされた。 花き業界ではどうだろうか。昨年の年末商戦を思い浮かべて欲しい。中国の神馬が大量に輸入され、単価も2L品で55円~65円の販売であった中で、国内の市場単価も下落し、厳しい状況が続いたことを思い出してほしい。また、1月は中国の産地の凍結で輸入が減少し、高い相場が続いたのである。これからは国内の産地として中国を見なければいけないのではないかと思う。ASEAN諸国も同様に国内産地としてみなし、産地間競争の相手として考え、勝利する『策』を模索しなければいけない時期がきているのである。花き市場も業界を守る意味でも、『自由貿易』について勉強し、その情報を的確に判断し、生産者の方々にも情報を流して、産地間競争にお手伝いするべきである。 経営環境が国際経済の動きによって、大きく変わるようになっていることは言うまでもないだろう。かっては地方の中小の花き市場の経営者の中で国際的な視野を持っている人は殆どいなかった。殆どの経営者は、その地方の枠内でしか、ものを考えていなかったが、今は違う。規模の大小を問わず、国際社会の動きに少なからず影響を受けていることを実感している。「ボーダーレース」の世界に対応するためには、人間の能力もボーダーレースである必要がある。多面的に、ものを見、より的確な判断を下すことができ、また柔軟な発想で新しい企画をどんどん出すことができる能力である。しかし、現実にはあくまで自分の専門領域に固辞し、その領域のことにしか関心が持てない会社の役員が多いのである(私も含むが)。 何故なら、世界のことが分からなければ、世界の中の日本の位置づけやその中の自分の業界のことも、さらには自社のことも、結局は分からないはずだからである。少なくても「自分の市場はこの先どう進んでいけばよいのか」を的確に見通すことはできないし、限られた発想で挑戦する範囲も小さく止まる。発想の原点を限定するのではなく、会社の部門別の外に原点を置くことによって、判断材料としての情報領域には限りがなくなり、きわめてグローバルな範囲に広がっていくのがあるべき形ではないだろうか。 |