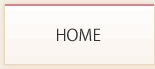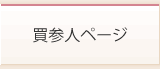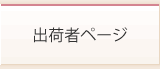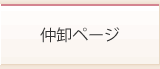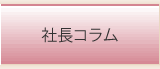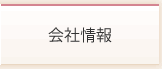IndexNo:245:数字の正確な理解なしには挑戦意欲も空回りする
|
1月に入り、また厳しい状況が続いている。末端の小売が完全に止まっていることで、この部門が苦戦している。葬儀需要が、今の相場を作っているのが現状である。私達の花き市場も売上が伸びるどころか減少していることは前にも述べたが、原因は何かということを追究してみたのである。それは入荷数量の減少にハッキリと出てきている。我が社だけではない、全国の花き市場でも「切花」の入荷が減少している。その全国の市場入荷数量をみると前年比96%位なのである。。 先日の営業会議において、営業の社員に「社長命令」として、過去5年間と今年の毎週のデータを提出し、営業会議等で検討し、「売れない時期」「売れる時期」の対応と「出荷時期の見直し」「生産品目の選定」などの問題解決において、今後どのように売上を伸ばしていくかを今年の目標としていくことにした。今までも色々なデータは取ってはいたが、各担当者の判断で動向を決定していたのである。営業社員も人の子である。相場が下がると「迷惑」を第一に考え、販売する気持ちが低下してしまう。いつのまにか、相場が下がってきて入荷が減少し、その入荷した数量が「適性なる数量」に変化してしまう。毎年のように売上が下がれば、この入荷数量が減少したまま「適性入荷数量」になってしまうのである。我が社は、売上減はここ1年だけなのであるから、今解決しなければいけない最も重要な問題なのである。 自社や自部門の販売、入荷という数字に弱い営業社員には次の欠点がある。①物事をあいまいにしかとらえられず正確な状況把握ができない。②物事を自分の主観だけでしかとらえられず、客観的な判断が下せない。③数字のデータを見てその意味を読み取ることができず、物事の本質をつかみ損なう。したがって、これらの欠点をもつ人は、間違いのない事業戦略を立てられるわけがないし、対外的な折衝(せっしょう)などの交渉事も有利に導くことができない。それどころか、営業という組織を誤った方向に向けてしまう可能性が極めて高いのである。 数字に強い、営業社員がデータをタイムリーにかつ正確に把握し、スピーデイーに的確な判断を下せる市場だけが競争に勝ち残っていくのではないかと思う。数字をつかんでいなければ、体外的にも社内的にもコミュニケーションの中身がだいぶ違うものになり、営業社員の日常の仕事にも影響してくるのである。当然、仕事の成果も大きく変わってくるはずである。 |