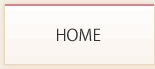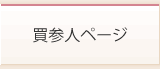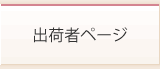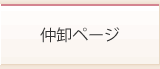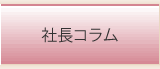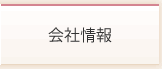IndexNo:247:ニーズが多様化することで市場が見えないの誤解
|
先日、福岡での会議終了後、懇親会の合間にホテルの部屋で衛星放送を観ていたら、中国の上海でのフラワーショップの事が放送されていた。何と驚くことなかれ、上海での始めての専門店だそうで、今注目を浴びているそうだ。それも中国初のショップの立地条件には二重の驚きであり、地下鉄の駅内にてオープンされていたのである。中国では低所得のために、今まで『花々』を家に飾ることなどなく、それが、近年の経済発展の成果で普通の家庭に金銭と生活の余裕ができ、生活に潤いを求めてきたということである。まさに生活習慣の変化(ライフスタイルの変化)である。 単価の設定であるが安いものでも日本円で15円からあり、高価なモノ(たぶんカサブランカ)でも150円位という。これから、多くのF・ショップの開店が計画され、全土に広がるとのことであった。今の日本の経済状況からは考えられないが、「中国で花き市場をオープンさせようかな」という気持ちになったことは事実である。中国という超大国が、これからの日本の花き業界の絶好の市場ターゲットになるおそれがあると予測するのは当たり前だろう。 ライフスタイルとは生活様式のことであるが、生活様式とはもともと多様化しているものであり、そうそう変化しているものではない。実際、あらゆる業界で多様化神話に基づき、多品種化を進めた結果、物流コストと製造コストの増大を招き、結局、品種をカットせざる得ない状態を招いている。多様化しているのなら、多くの品種がまんべんなく売れるはずなのに、そうはならなかったということである。 あえて、多様化している部分があるとすれば、それは購買行動に関してであるが、そこまで踏み込んだ議論はなされてない場合が多いのである。このようなイメージが先行した意味不明の言葉が社内をひとり歩きしていないだろうか。今、必要なことは、客観的な立場で顧客のニーズを論じることではない。まず、「顧客と同じ立場から、自社の販売商品を見直し、評価することなのである。そういうことが、花き業界の発展につながるのではないかと思う。 |