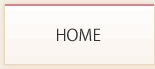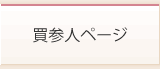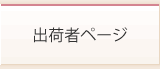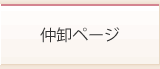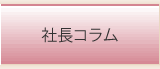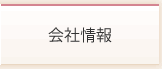IndexNo:248:『現場は末端』でない
|
1月も、市場売上が落ち込んだ結果になってしまった。昨年は菊類、百合類が高値で取引され、1月にしては中々の売上を計上できたのだが、今年は、寒気の影響もあって小売がダウンし、たよるものは葬儀需要だけになってしまった。鉢物もこの寒さでは売れるはずがないだろうし、ショップや園芸店などは厳しい状況が続いている。となると、暖房費などの経費が膨らみ、コストがかかる時期に出荷する生産者も、おのずと比例して、厳しくなってくるのである。ネット(Web)販売も低調であり、防止対策以上の小売減の波が大きく、不安であることは間違いない。 先日、ある生産者の会合に出た時の話であるが、生産者の方から「宮崎は社長自ら働きになる。私が取引している他市場では、セリ中に社長は机で居眠りをされていますよ」と言われた。また、ある方は「最近は、現場で働く役員の方々が減りましたね」ともおっしゃっていた。 「現場を知れ」「現場の声を聞け」と昔からよく言われる。これは、何が問題なのかを「現場」が雄弁に語ってくれることを示しているのではないかと思う。言い換えると、現場とは市場にとって解決すべき問題の宝庫でもあり、そして、その解決策(答え)も、また現場にあるということなのである。あくまでも顧客との接点、利益を生み出す原点としての「現場」が経営の原点でもあるのである。「お客様の立場から、自社はどうあるべきなのか」を考えるためには、欠かせない視点でもある。 三現主義と言われ『現場』『現実』『現物』をもとに物事を考えるというのは、ホンダの経営理念として有名であるが、業種や規模を問わず、経営の基本である。実際、「現場が最大の財産です」と思うのであるが、だから、私自ら現場で働くことを実践している。現場を見ていないと、お客様に対する見方、事業への考え方がマンネリしてくるのである。厳しい状況が続く今こそ、役員を含めたすべての社員が、現場主義を徹底し、理屈ではダメだということを知らなければならない。 頭のいい人間ほど、聞いていてなるほどと思わせる理屈を言うが、現場を知らないニセモノの机上の計算は何も変えることはできないのである。忘れてはならないことは、現場とは非論理的なものであるということ。言い換えると、現場とはもともと理屈に合わないものなのである。そこに理屈を当てはめようとするから、意味のない、つじつまあわせになってしまうのだ。不振打開にも、市場革新にも『奇策』はないのである。よく言われる『原点に戻れ』というのは『現場に戻れ』と同義語であるのである。 |