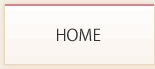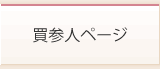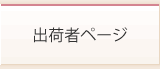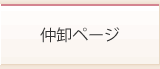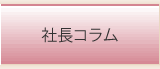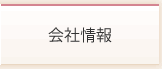IndexNo:265:『業界の常識』の誤解
|
例年なら母の日を過ぎると切花は冬商品が徐々に減少し、6月にもなると平地物は一部洋花を除いて夏商品(高冷地物)が増加傾向になる。代表的な物に例えると白菊では、神馬から優花に変わってくるという感じである。鉢物に関しては、先日、他県の花き市場の社長との会話の中で「鉢物は入荷減の連続で単価も厳しいですわ」とのお話を聞かして頂いた。母の日が過ぎると入荷量が減少してくることが我々花き市場業界の常識なハズであるが、当社では鉢物の入荷が減少しないどころか、逆に増えつつある。県外の商品の入荷増によるもので、担当に聞いてみると「今年はこの時期の入荷は減ることはないですよ。昨年の二の舞を踏まないようにと、一年間努力してきました」との返事が返ってきたのである。こういう返事がサラリと返ってくると「成長してきたな」「我慢してきてよかった」と思うこの頃でる。 市場は入荷されたものを販売するという常識から脱皮し、顧客が欲しいものを販売していく姿勢を示していかなければならないと思う。6月より東京の大田花きのオリーブと当社のスリーディズを利用し、当社の顧客が大田花きの商品を購入できるシステムをスタートさせる。他市場から当社への非難の声を聞いたりするが、私は思う。顧客が本当に望んでいるものを揃えることができれば何ら問題ないのだが、地方のローカル市場である当社では、めまぐるしく進化していく商品の入荷はゼッタイに無理である。逆に日本の中心に集まる商品を『この目』でみて、生産者への情報源としていくことが得策ではなかろうかと思うのである。また、相互のネット(Web)を利用することで宮崎の花を全国に販売できるチャンスでもあるのだ。要するに、顧客が欲しいものを揃える。生産者が運賃などのリスクを背負わず安定した価格で販売できることがベターでなかろうか。 それぞれの業界には、その業界の常識というものがある。「業界の常識を破った・・・」などと言われるが、そう言われること自体、業界に常識なるものが存在するということの証明であると思う。「花き市場業界にはこういうものがあり、こうするしかないのだ」という常識である。しかし、その業界の常識に合理的な根拠があるかといえば、必ずしもそうではないのである。例を言えば「引越し」専業の業者はどうであろう。年間を通じてコンスタントに需要がないから事業にならないという常識をくつがえしたのではないか。 今回の当社の事業は必ず成功するという確信を持っている。何故なら、顧客(買参、生産者)の利益が出れば、その利益の一部がいつか必ず、私共の市場に帰ってくる。それが商売の原則だと思う。前に事例としてあげた「引越し」もそうだが、新たな変革の芽は足元にあることが多いことに気づく。それは、従来の事業のやり方を疑ってかかることによって、しばられていた業界の常識を打ち破ることができたためだろう。 |