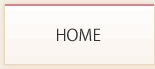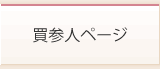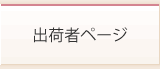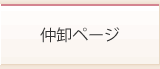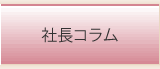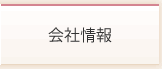IndexNo:266:「ローカル市場だから大手並みにはムリ」の誤解
|
6月に入り、梅雨入りの影響などで相場が低迷している。一部の市場では価格が上向いているとは聞くが弊社では今週も厳しい状況である。入荷も暖地物と高冷地物の入れ替えが平年通りにはいかず、毎セリのように増減が続いている中で、今日の台風でかなりの入荷減になり、売上に於いてダメージが大きすぎる結果になってしまった。尚、セリが終了したときには青空が広がり、かなりのショックであった。この台風が四国、本州と向かえば、それぞれの市場も苦戦するに違いないと思うが・・・・・。 水曜夜に大田花きから2名、大森花きから2名来訪して頂き「オリーブを利用したネット(Web)取引の説明会を開催したのである。買参人も当初の予定をはるかに上回る70名余の参加をいただき、この取引の注目度の高さを感じた。また、数社の市場から色々な意見を頂いたが、私としては新しい取引(新規戦略)として続けていきたいと思っている。何ひとつ動きをしないで顧客に逃げられるか、動くことで顧客が今以上に伸びてくれるかがポイントである。 中小の花き市場ほど、資金不足、人材不足、設備不足などをはじめ『不足づくめの経営』のマイナス面だけを見て「いたしかたない」とあきらめてしまいがちである。経営にはことさら『新しい技術』が必要なわけではないし、大型市場にしかできないというようなことは一部を除き極めて少ない。当然のことを当然のようにやるだけで成果が出るのが経営というものではなかろうか。分かりやすく言えば、朝の時点で、今日一日どういう動きをしてどれだけ販売していくかということが、一人ひとりに徹底されているかどうか、ということである。それさえ明確であれば、社員の動きは違ってくるはずなのである。 「社内を活性化せよ」と言われるが、尻をたたいたり、ガンバリズムで気勢をあげる、といった一時的な応急処置のようなことで会社は活性化しないし、三日坊主で終わることも多いのではないか。一時的な活気を招くことではなく、「やるべきことを確実にやり続けること」それが活性化の意味なのだと思うのだが。どうであろう。未熟な環境の中で、最善の努力をするからこそ、人が育つのである。また、社員を一人二役、三役で活かす中小の花き市場の中から成長する会社が誕生してくるのではないかと思う。 |