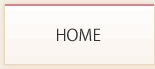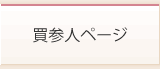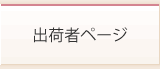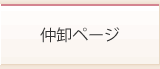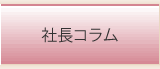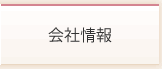IndexNo:267:商品の人気はエンドユーザーが裁定する
|
今週に入り、高冷地物が徐々に入荷増の状況ではあるが、まだまだ本来の集荷態勢ではない。しかし、一部商品を除き安定した価格で取引されている。高値で取引されているものに菊類があるが、とにかく上場数量が極端に少ないために100円を越す相場で生花商の方々に多大な迷惑をかけている。来週後半には平常の入荷になるので、しばらく辛抱してもらわないといけない。とにかく5月も6月も厳しい状況であることは間違いない。 前にもこのコラムで書いたことがあるが、輸入商品の品質と鮮度が国内品と変わらない位、良くなってきている。先月も隣県の花き市場で韓国のバラの話を聞き、その商品を購入されている仲卸に品質、人気度について尋ねてみた。ボリューム、長さ、花形、花弁肉質等申し分なく、人気商品とのこと。エンドユーザー(一般消費者)にも、韓国のバラという指名された品種商品があるとのことで、その人気に正直驚いた。エンドユーザーの生の声は、貴重な情報でもあり、最高の財産でもある。顧客が好きな花々を購入されることは、ごく普通な事であり、それを仕入し、提供する。たとえ、国内産であっても顧客に受け要られなかったら、不人気商品として取り扱われることになるだろう。顧客の満足度のためにも産地表示を考えた方が良と思うのだが。 他業界の話であるが、ここ10年間、店舗の数が激減しているそうだ。「○○屋さん」というものが本当に見られなくなってきていることは、読者の皆さんも周知の事実である。顧客に何でも売ればいい、購入してもらえばいいという「いらっしゃいませ主義」の結果がこのような現実をつくってきたと思う。この『結果』のもっとも大きな弊害はマイナス発想になってしまうということである。とりわけ、できそうなことはすべてやり尽くした『つもり』になってしまう。物事のマイナス面だけを見てしまうから、正しく判断できず、正しく行動できないのである。つねに『時』は動いているし、顧客の欲しい物も変化してくる。顧客に提案し購入していただき、リピーターとして来店してもらうことが勝ち組の基本ではなかろうか。当たり前だと思うことや常識だと判断することに落とし穴がある。では、そのようなことを100%実践しているか、考えてほしい。 |