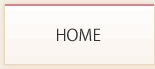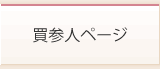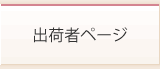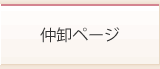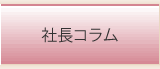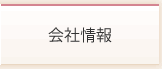IndexNo:287:より大きなロスから具体的に退治する。
|
入荷量が激減している。社員からも「台風で○○○であるから」と返事が返ってくる。大分、福岡からの荷物がトラック便が台風で集荷ができない関係で、入荷量が減り、売上が激減した。何か対応策は取ったのかと聞いてみると「やった」という。しかし、鹿児島や都城にはその産地の商品が、自社で集荷などをして入荷している事実がある。これがダメだったらあとは全てダメということになる。問題解決のアクションを起こす時というのは、一人ひとりが「こんなことでは・・・」という危機感や、「自分が何とかしなければ・・・」という使命感を持つときである。 要するにアクションを起こさないというのは、そのような危機感や使命感を持つまでに問題意識が高まっていないということである。そもそも問題意識を持つ時というのは、他市場との比較、過去の実績との比較、未来の目標との比較などによって、まだまだと感じる時である。注意しなければならないのは、比較するときに、決して自分を甘やかさないことである。「他の市場もたいしたことはやっていない」「我が社はまだ利益をあげているし、あせることはない」と言った考えは危機感、使命感を弱めていく原因となる。例えば「台風で荷物が少ない」という結果を問題として意識するときにまず、他市場との比較などによって現状の1.2倍から1.3倍まではもっていかなければならないと定量的に入荷量を把握することだ。具体的な問題意識を持つことによって最初の方向付けが決まることになる。 次に『具体的なロスの追求』である。「入荷が少ない」という結果として会社にどのような具体的なロスをもたらすのかということである。昨年比90%と95%とでは、人件費や諸経費にかかる費用の負担、新規営業戦略への投資負担がどれくらいの差となるのかである。さらに、その結果を踏まえて、「この問題は解決するに値するのか」「問題解決にどれほどの時間、経費や努力を投入する価値があるのか」を判断しなければならないのである。たくさんある問題のすべてに手をつけるわけにはいかない。効果をあげるためには、重点的にエネルギーを投入することが必要である。具体的なアクションを起こすためには段階的に問題を追及し、問題意識を高めていくことが必要なのである。私自身、今回の台風飛来によって、多くの要件を学ぶことになった。 |