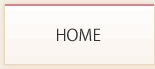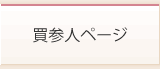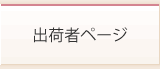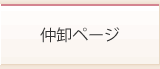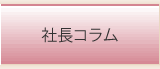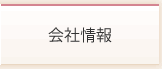IndexNo:296:伸びるJA産地は100%協力体制ができている。
|
12月に入り、松市が7日に行われた。販売単価は例年並みで推移し、入荷量を3万本増加した分が売上増となった。菊類や洋花は今週から来週に掛けて、小売が苦戦するときでり、葬儀や婚礼などの仕事花に頼る時期に突入してきている。相場も昨年と比べ安定しており、年末商戦前の静かな動きであることは間違いない。来週の企画市(千両・南天等)が過ぎれば、多忙な毎日が続くだろう。 先日、鹿児島の「JAそお」から大菊・SP菊関係の生産者の方々が、前日から懇談会・市場視察を含めて来訪された。懇談会では宮崎の葬儀関係に納品する2社の代表者から、お話をお聞きできる時間を当社の担当者が作り、有意義な懇談会となった。私も若い生産者の方々と話をして、今後の生産に対しての要望等を伝えることができたのである。 その中で、生産者の方からこんな話を聞いたのである。「台風16号の前に、今日から花切りが始まる、台風の対策を早急にしていかなければならない時に、私の母が脳内出血で倒れたんです」「JAの永次長や近松さんや普及所の方が集まってくれて、お前は病院に行け!、後は俺達でやるから」と。最終的には、毎日のように夜中まで仕事を続け、出荷も台風対策も全て終わったということで心から感謝されていた。確かにJAそおに関しては、生産量や販売額が驚異的に伸びている優秀な産地である。産地も大きくなると、細部にわたって連携が取れなくなってくるのは当たり前のことであるが、永次長や他の関係者が産地を「大事に育てる」という面では他の産地関係者も見習いたいものである。やはり、大きく伸びる産地というのは、行政やJAの指導において協力体制が整っていることをつくづく感じた。 モノの見方、考え方、仕事に賭ける使命感、深い思考力、仕事への姿勢など、長い目で見れば必ず成果につながる能力であるが、一朝一夕には実現できないのも確かである。その成長ぶりが計れないだけに、生産者や人々を育てようという意識が希薄になることが多いのである。しかし、そんなことは言ってはいられない、産地の将来を担っていくのは、間違いなく今の指導者のもとで勉強する生産者たちなのである。それだけに指導者の資質やリーダーシップなどが問われるのでないかと思う。いつも言うことだが、誰にでもできることを当たり前のように達成することは難しい。産地の担当の方が判断することだが「俺でもできる」と「俺にできるかな」もう一度産地作りを考えていただきたいものである。 |