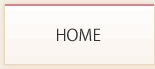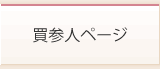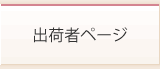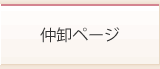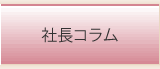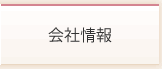IndexNo:338:多くの市場も倒産に向かって進んでいる。
|
今週は、入荷減において大菊、草花系を中心に強含みで取引されている。但し、大菊を中心とした菊系が東京及び東日本の花き市場において下げ相場の状況であり、今後は当社でもその傾向が出てくるものと思われる。また、台風14号での入荷減、単価安の影響にて9月末の累計売上及び利益率も低下して、損益分岐点比率も下げてきているのが現状であり、10月からの「動き」に期待しているところである。 ところで、損益分岐点比率についてお話してみたい。損益分岐点比率とは、固定費を限界利益で割り×100の数字が60%以上で安泰であり、60%~70%で健全.70%~80%でやや健全という数値がでてくる。また、限界利益とは売上高-変動費であり、固定費とは販売費.一般管理費.支払利息等のマイナス雑収のことを意味する。また、損益分岐点の売上高とは「収支トントンの売上高」の意味でこの損益分岐点の売上高以上であれば、利益が発生し、それ以下だと損失になってしまうという、会社の経営上の指針となるべきものです。 どんな市場でも、企業というのは宿命的に「倒産に向かって進むエネルギー」を持っている。今回の台風等の環境の資的な変化や顧客ニーズの変化や競争状態等に対応して、常に打つ手を変えていかなければ、業績は下がっていくこととなる。経営者は、このことを充分すぎるくらい知っているはずだ。だから、業績が好調な時でさえ、いつおかしくなるか分からないという危機感を常に持ち、たとえ業績が落ち込んでも、そのとき慌てないだけの準備を心がけ、一瞬たりとも気が休まることはない。言い換えると、経営者の毎日とは『倒産の現実と戦い続ける毎日』だと言えるのではないかと私自身、真に認識している。 経営とは、どの市場も例外なく持っているこの「倒産に向かって進むエネルギー」を上向きに支え続ける力である。変化にあわせて事業の中身や方法を変えていくということである。少なくても、その経営の中枢を担っている役員などの管理職のレベルでは『市場は環境の変化に対応して変化しなければ必ずつぶれる』という危機意識は肌で感じられるようでなければならないのである。 |