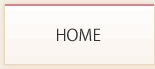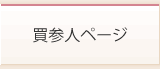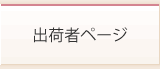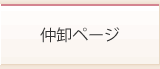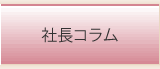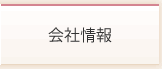IndexNo:363:マネジメントと花プログラムの勉強の必要性
|
先日、九州管内の花き市場の17年度の取扱高を確認することができた。10億以上の市場規模で取扱高が軒並み5%前後減少している。また、年間1億~5億の取扱い市場は現状か微増の結果となっていた。取扱高が減少している市場では、原因として花商及び取扱数量の減少と単価の下落があげられるようである。花き業界のマーケティングについて考えてみると、需要と供給のバランスが崩れているのは間違いない。決定的に言えることは、長期的な結果として、供給が減少すると価格は上がるのがふつうであり、今の業界では供給する、すなわち取扱数量が減少しても単価は下落している現状でこのことが言えるのである。 この2.3年サプライチェーンという言葉を耳にする方も多いと思う。このサプライ(供給)チェーンとは、業界に置き換えてみると生産から消費者までをつなぐ、より長いチャンネルを意味する。サプライチェーンは、価値提供システムであり、企業はサプライチェーンによって生じる総価値の中からある程度の利益を得るにすぎないのである。企業がチェーンの川上部門(生産)か川下部門(販売)に移行したりする場合、その目標はサプライチェーンが生む価値からより大きな利益を得ることができるのである。 今、フィリップコトラーの『マーケティング.マネジメント』を読んでいる。やはり、業界を基本から考えていくためには、マーケティング全般を知る必要性がある。20世紀から21世紀へ。そのマーケティングも目まぐるしく変化してきている。上記で述べたとおりに、国内の花き市場の取扱高が厳しい状況の中で、飛躍する要因を見い出していくには、今までの経験も大事だと思うが、やはり「花」というひとつの価値プログラムを勉強することが必要だと感じている。今、私達の世代が実践し、その結果で残したものを後継者に引き継がれるのである。この業界が衰退しないためにも『業界で経験した以外の知識』が必要だと思っている。取扱高が上がった、下がったと仲良くクラプで話している場合ではないのである。 |