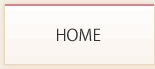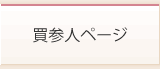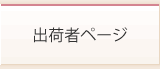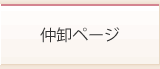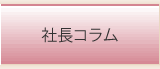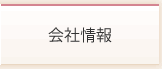IndexNo:367:「花き市場には特殊な事情があるの誤解」
|
今週、草花・球根系は好調に販売されてはいるが、菊類だけはセリ人を悩ましている。年末の二度切り分が国内の市場に溢れて、どの市場も苦戦している状況である。鉢物は、母の日前の週ということで草花・洋花関係が引合が強く、カーネの鉢物は気温高の影響で弱含みで取引されていた。昨年は、母の日が連休明けの8日ということもあり、思うように小売で売れなかったが、今年は商戦が連休明けの1週間であるので買参・仲卸とも昨年比の120%の売上増を市場としては期待している。 先週に地元銀行主催の経営セミナーがあり当社の常務を出席させた。その資料を読んでみて思うことがあった。これからは、団塊の世代をターゲットにしていくビジネスが増加しそうである。大都市の花き市場やショップ等は、今後それらのユーザーを見据えて商戦を仕掛けてくるものと思われる。地方ではどうか、一部の花き業界の方々や青果・水産関係者とお話をしても、そのことについて意識すらないのが現状である。また、地方の市場関係者と話をしても「我が社には特殊な事情がある」と逃げ道を作っていく。 何をもって、「特殊」と言っているのかは不明である。営業方法、ターゲットにしている顧客層、商品の単価、商品の日持ちと違いをあげていけばキリがない。そもそも特殊な販売方法、特殊な商品、特殊な顧客層・・・などが存在するだろうか。そのような特殊な事情を認めてしまえば、すべての企業は特殊ということになると思うが?。もし、まったく同じ条件の会社での成功例でなければ参考にならないというのなら、外部の知恵はほとんど使い物にならないと思わなければならない。 今、積極的に他業界の成功事例に学ぶ姿勢を持たなければ「発想」の袋小路から抜け出すことはできないであろう。肝心なことは、自社が置かれている状況を特殊と見なすのではなく、他市場の成功事例や失敗事例を自社に置き換えてときに、どのように応用できるかを考えることであると思う。中小の花き市場が大都市の大型市場の成功事例に学ぶこともできるし、その逆もあるはずである。問題は自社に置き換えたときに、具体的な策としてイメージできるかどうかである。 |