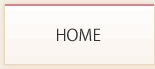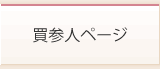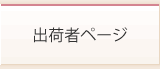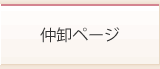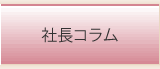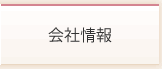IndexNo:373:マーケティングロジスティクスの問題を克服する。
|
今週、降雨の為に末端の小売がストップして、切花では洋花類、球根類が下げてきた。鉢物も先週よく売れた苗物を中心に全体的に下げてきており、順調に推移してきた相場も厳しくなってきている。菊類も多雨の影響にてサビ入りのものが入荷している状況で秀品の商品が入荷不足にて100円の価格で今日は販売されている。先日、西日本花き市場懇談会の翌日に高松花市場に視察に行ってきたが『喉から手が出る?」ような大菊他が○○円で販売されており、今年の九州の多雨の影響が単価の違いを象徴しているような気がした。 7月から来年の1月~4月の大菊の生産体制の準備に入るつもりでいる。当社では前年比150%の入荷、生産体制を計画している。もちろん重油の高騰でコスト高になることを承知の上での生産増を狙っていく。買付集荷となるために様様なリスクもあるだろうが、ある程度の資金を準備して単年度赤字でもやっいく覚悟である。県内外の生産者との契約や協議になるだろうが、当社への期待は大きく生産者の方々の注目を集めているのが現状である。 100億を越す取扱高を誇る大型市場では、集荷でのセリ売りの率が50%を割るそうだ。相対取引やネット(Web)取引において、年々セリ場での上場率が減ってきているのが当たり前になってきている。勿論、当社や他の市場も50%と言えないまでも相対販売の比率が増えてきているのも実情である。そうなると事前情報の勝負であり、売り先と出荷先との駆け引きもあるが、最終的には、買い手が欲しい時期に欲しい量の商品を供給できるマーケティングロジスティクスの問題でもあると思う。 個々の生産者が同じ地域の産地では、出荷時期が同じになるし、出荷時期の調整となるとロットの問題が出てくる。県内外での気候の違いにて出荷時期が変わる産地づくりや顧客の要望にあった品種産地を形成していくことが私に課せられた問題となってくるので、社員同様『足で稼ぐしかない』と思っている。目標が次から次へと出てくることは社員は大変だと思うが、これを成し遂げていかなければ会社の発展はないし、給与も上がらないのである。 |