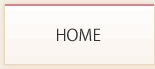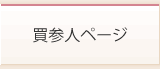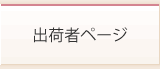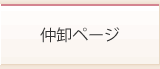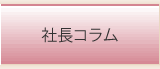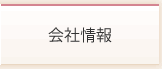IndexNo:415:中途半端な指示はやめる
|
今週は、切・鉢とも来週からの彼岸商戦に向けて、全体的な流れを止めずに中値安定での販売を目標とした。一部の商品は厳しかったが、小売需要に押され来週本番に向け、よいスタートとなったと思っている。 今年の目標に「セリ場の活性化」を掲げているが、ここ3週間は、この活性化の為の会議を行わずにいる。それは、お彼岸の為の営業会議等を優先しているためだ。彼岸商戦を前に相対販売での処置の仕方を「臨機応変に対応しなさい」との指令を出している。昨晩もこの相対について考えてみたが、営業社員に対して「臨機応変に」と指令した自分に無責任さを感じている。 人が持つ判断基準というのは、それまでの経験や知識などの違いによって、実にさまざまであり各人格での基準を持っている。簡単に言ってしまえば、バラツキがあるのが当然なのである。とりわけ、私達管理職と営業社員の間には相当なギャップがあるのである。従って「臨機応変に対応しなさい」といった指示の出し方は、かなりの問題があるのだと思っている。日頃から「先をよんで動きなさい」と言ってはいるが、その一手先の読み方からして個人差がある。私達が「どうしてこのような場合にこうしないのだろう」などと社員の対応に不満を持ったとしても、『キャリア』が絶対的に違うのだから仕方がないのである。その個人差を解消するには、私達と社員が一緒になって考える必要があるのではないかと思っている。 現時点で考えられる状況を想定し、その対応策を一緒に考える。この「一緒に考える」というプロセスを省略してしまうことは、「あとは任せた」といえば聞こえはいいが、私達管理職自身が考えることをやめてしまったことになると思うのだが・・・。深く考えてみると、判断と責任を営業社員に押し付ける格好となってしまうのである。「こういう状況になったらこうしよう。こういう場合はこういう手もある。それ以外の状況が発生したら、もう一度二人で検討しよう」というやりとりがあって、はじめてノウハウの伝授も可能になるし、ハッキリとした方針のもと、社員も自信を持って取り組むことができると思うのです。 それを「臨機応変に・・・」などとやるから、場合によっては、ズルイとみられたり、責任転換をしていると思われたりするのである。営業社員にも総務担当の社員にも『中途半端な指示』はゼッタイに避けなければならないと感じた。この思いを当社の役員の方々は理解してくれているのか・・・。 |