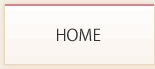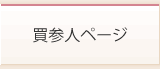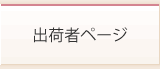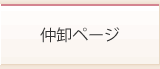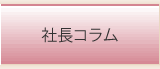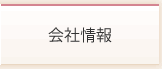IndexNo:447:訪問件数が業界を救う
|
今週は、高冷地物と暖地物の入替の時期でもあり入荷が減少傾向にある。隣の鹿児島でも大菊の入荷が極端に少なく(仲卸いわく過去初めての状態)、当社と同じ位の単価で取引されている。今朝もストック・アイリス産地のJA担当者が来社され、お話しできたが、11月から本格的に出荷ということで、後7日~10日位は、菊類・洋花類と入荷減での取引となりそうだ。鉢物は、パンジー苗を中心とした花苗の販売が主力となり地元産を中心に草花・洋ラン類と多種多様な入荷により活発に取引ができそうである。気温も低くなり秋・冬シーズン到来での販売に期待しているところでもある。 青果・水産市場では、買参人の数がオープン当時の半分以下になっているという。もちろん生産者(出荷者)も高齢化や経営上の問題で減少している。花き業界は新規就農・後継者問題は進んでいるもの、2.3年後は同じ傾向にあるものと思われる。では、花き市場では「何をなすべきか」という問題になってくる。そうなると、いつも言って実践させているように『足で稼ぐ』ことであると思っている。営業活動で重点を置くべきテーマは「訪問件数」である。新規開拓や深耕開拓かを問わず、訪問件数を増やさない限り、成果が出ないことだけはハッキリとしている。もちろん内容の伴わない訪問では、いくら件数をこなしても意味はない。されどー訪問件数」なのである。 目的を持った「訪問」をしても相手に伝わらない場合もある。そうなると「何回も足を運ぶ」ことが目的から成果になる最大の解決方法となるのではないか。買参の場合は既存の店舗の奪い合いとなり、より購入しやすい・うまみのある市場を選択してくるが。生産者の新規開拓は、今後の大きな目標であることは間違いない。そういう観点からみると行政・JA等の協力も必要となってくるし、資金面での対応も大事な面ではなかろうか。この件に於いては、地元の2銀行も農業分野での資金貸出は、ハードルが低くなってきているので、紹介・協力できると思っている。花き市場の原点である、売る(出荷者)・買う(買参、仲卸)の狭間で商いを行うことを忘れずに社員全員に伝え、尚且つ業界発展の為に努力していこうと思っている。 |